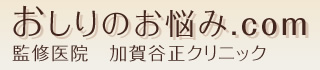
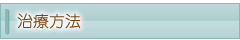
痔の治療方法について
痔の治療において、最も重要なのは生活習慣の改善です。
軽度の痔であればこれだけで治ってしまうことも多いです。 逆にせっかく手術をしても術後に不摂生を繰り返していると、痔は再発します。術後も肛門に負担をかけない生活習慣を心がけてください。
中程度以上の痔には手術が必要です。
手術法には
1.ゴム輪結さつ法
2.結さつ切除法
(従来からある痔を切って取る手術です)
3.PHH
4.ジオンによる硬化療
があります。
PPHやジオンによる硬化療法は痛みが少なく、日帰り治療が可能です。
最近では痔を切る結紮切除法でも痛みを少なくする工夫がされ、日帰りや1泊入院で治療できるようになりました。
軽度の痔であればこれだけで治ってしまうことも多いです。 逆にせっかく手術をしても術後に不摂生を繰り返していると、痔は再発します。術後も肛門に負担をかけない生活習慣を心がけてください。
中程度以上の痔には手術が必要です。
手術法には
1.ゴム輪結さつ法
2.結さつ切除法
(従来からある痔を切って取る手術です)
3.PHH
4.ジオンによる硬化療
があります。
PPHやジオンによる硬化療法は痛みが少なく、日帰り治療が可能です。
最近では痔を切る結紮切除法でも痛みを少なくする工夫がされ、日帰りや1泊入院で治療できるようになりました。
痔の手術方法について
全ての痔に全ての手術法が適応できる訳ではありません。それそれの痔のタイプに応じて、手術法を選択します。
初期の内痔核で出血だけが症状の場合には、ゴム輪結紮法やジオンによる硬化療法を行います。
肛門の外側にまでしこりが広がっているような場合には、結紮切除を行います。
肛門全周に痔が脱出するような症例には、PPHが最適です。
また、痛みや出血などの合併症が少なくなるように2つ以上の手術法を組み合わせることもあります。
初期の内痔核で出血だけが症状の場合には、ゴム輪結紮法やジオンによる硬化療法を行います。
肛門の外側にまでしこりが広がっているような場合には、結紮切除を行います。
肛門全周に痔が脱出するような症例には、PPHが最適です。
また、痛みや出血などの合併症が少なくなるように2つ以上の手術法を組み合わせることもあります。
PPH法とは
特殊な器具で肛門の奥を2cm程切除し、たるんだ肛門粘膜を引き上げます。
ズボンがずれ落ちて、足元にたるみができた状態を想像してみてくだ さい。
膝の辺 りでズボンをたぐると、足元のたるみはなくなりますね。
これと同様に直接肛門を手術するのではなく、その奥を切って裾上げすることにより粘膜のたるみを治 してしまいます。
肛門の奥は狭く直接切るのは難しいため、筒状のメスやホチキスのように縫う機能が内蔵された特殊な器具を使用します。
痛みを感じる神経が ない部位を切除するので、術後の痛みがほとんどないのが特徴です。日帰り治療ができます 。
ズボンがずれ落ちて、足元にたるみができた状態を想像してみてくだ さい。
膝の辺 りでズボンをたぐると、足元のたるみはなくなりますね。
これと同様に直接肛門を手術するのではなく、その奥を切って裾上げすることにより粘膜のたるみを治 してしまいます。
肛門の奥は狭く直接切るのは難しいため、筒状のメスやホチキスのように縫う機能が内蔵された特殊な器具を使用します。
痛みを感じる神経が ない部位を切除するので、術後の痛みがほとんどないのが特徴です。日帰り治療ができます 。

▼

筒状のメスと、ホチキスのように縫う機能が内蔵された特殊な器具を使用します。
▼

特殊な器具で肛門の奥を2cm程切除します。
▼

たるんだ肛門粘膜がひきあげられ、痔が治ります。
痔の合併症について
痔核手術の合併症としては、次のようなものがあります。手術法により多少の差異があります。
1)後出血(結紮切除やPPHの手術の7日から10日後に、出血を起こすことがまれにあります。)
2)化膿
3)肛門狭窄、直腸潰瘍
4)発熱(ジオンによる硬化療法でまれに術後の発熱が報告されています)
いずれも可能性はごくわずかで、リスクの高い手術ではありません。
手術の安全性には十分に配慮しておりますが、実際には合併症がゼロという手術はありません。合併症のおこる可能性については十分にご理解いただく必要があります。
1)後出血(結紮切除やPPHの手術の7日から10日後に、出血を起こすことがまれにあります。)
2)化膿
3)肛門狭窄、直腸潰瘍
4)発熱(ジオンによる硬化療法でまれに術後の発熱が報告されています)
いずれも可能性はごくわずかで、リスクの高い手術ではありません。
手術の安全性には十分に配慮しておりますが、実際には合併症がゼロという手術はありません。合併症のおこる可能性については十分にご理解いただく必要があります。
痛みを和らげる対処法
 冷やす
冷やす 患部に炎症が起きている場合は、腫れや痛みがひどいうみ痔であることが考えられます。
下着に膿や分泌液が付着するうみ痔は、かぶれやすく激しい痛みと共にかゆみを感じることも多くあります。かゆみは冷やすことで軽減させることが出来ます。
しかし、分泌液や膿が肛門周辺に付着したままですと、一時的にかゆみを軽減させても意味はありません。分泌液を定期的にぬるま湯で洗い流し、しっかりと乾燥をさせてからアイスノンなどで患部に当てて安静にしておくとかゆみは治まるでしょう。
しかし、痔の治療では本来冷やすことは良くありません。かゆみや痛みが治まったとしても、必ず医療機関で受診して下さい。
 温める
温める肛門の周辺の血行が悪くなっている場合には、症状がひどくない時でも患部を温めることが重要です。
特に痛みのある「内核痔」の場合など、カイロや温めたタオルなどを患部に当てて安静にしていると急激な痛みを和らげることも出来ます。
痔核や裂肛は、同じ 姿勢でいる状態や冷えにって起こる、うっ血が大きな原因になっていますので、毎日の入浴でしっかりと湯船につかり、患部を温めて血液の循環を良くすることで症状を軽減させ、進行を予防することが出来ます。
しかし、急激に血液の循環が良くなり反対に症状がひどくなってしまう場合もありますので注意しましょう。
 姿勢
姿勢痛みを感じて患部を温めたり、冷やしたりする際はうつ伏せになるのが一番です。
しかし、身体をまっすぐに伸ばすのが辛い場合もあります。うつ 伏せになるのが辛い場合には、腹部に丸めた毛布などを当てて身体を預けるようにすると力を楽に抜くことができます。
また特に冷やしたり、温めたりしなくて も、しばらく安静にしているだけで痛みを和らげることができます。
腹部の圧力が掛かることで痛みを感じることもあるので、横をむいて膝を曲げ、身体の力が抜ける姿勢をとりましょう。
しかし、あくまでも痛みを和らげる対処法でしかありませんので、痛みが治まったら医療機関でしっかりと受診して下さい。

◆ 監修医院について
◆ アクセス
◆ 痔という病気
◆ なぜ痔になるの
◆ 痔の種類
◆ 治療の流れ
◆ 治療方法
◆ 切らない痔の治療
◆ 痔Q&A
◆ 症例
◆ 治療費について
